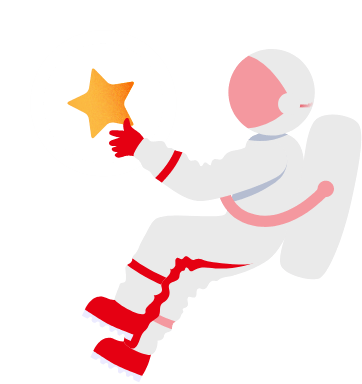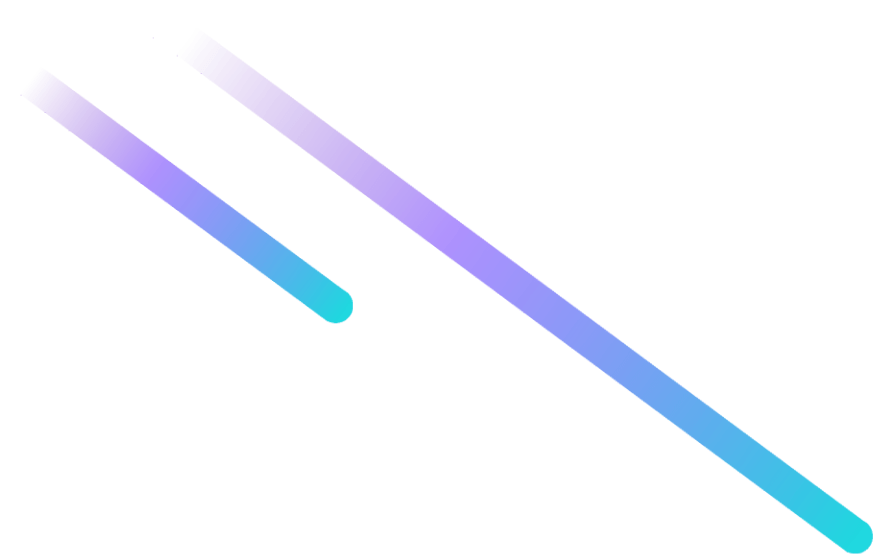
 01
01待ち望まれた
新たな“スター”の誕生
ヤマザキビスケットのスナック商品に、ポテトに代わる新たなスターを。ポテトスナック「チップスター」という人気ブランドを持つ同社では、長らく第二の主軸となるスナック・ブランドの誕生が待ち望まれていた。2009年8月、そこに登場したのがコーンスナック「エアリアル」だ。当時入社3年目のUは、そんな「エアリアル」開発メンバーの一人だった。Uは製造ラインから新商品を生み出す開発研究室に異動したばかり。連日の試行錯誤が続く中、スタッフが集まってのミーティングで、ミルフィーユのように4層に重ね合わせる案にたどり着いた。これこそ、「エアリアル」が生まれた瞬間だった。
「アイデアの中から商品化するまでの流れを見届けたのは、『エアリアル』が初めてでした」。Uは懐かしんだ。「開発に来て、毎日あーでもない、こーでもないと皆で練りに練って、ついに満足いくものが出来たんです。当時は仲間うちで『かるっと』と呼んでいましたね」。

独自製法の新商品は
発売間もなく大ヒット!
ところが…
薄いコーン生地を4枚重ね合わせた軽やかな食感。「完璧な作り込みだ。これならいける」。新製品会議で初めて「エアリアル」を口にした商品開発課のSは、確信した。いつもと違う手ごたえを感じたのはSだけではなかった。会社全体が「エアリアル」のおいしさに沸いていた。
「これはきちんと育て上げさえすれば、定番商品として根付かせる力を持っている」。商品を売り出す戦略を立て、ブランド全体をコントロールしていくのが商品開発課だ。そのマーケティング担当として、Sの心はいつになく高揚した。
量販店は新商品というだけですぐに棚に並べてくれるわけではない。しかし他社商品にはないおいしさと独自製法を全面に出した狙い通りに、「エアリアル」は発売当初から順調な滑り出しを見せた。採用基準が厳しい大手コンビニの店頭にも並び、社内のお客様相談室には「おいしい」「どこで売っているのか」など問い合わせが相次いだ。その件数はこれまでのどの新商品よりも多く、群を抜いていた。「しお」「チェダーチーズ」「焼きとうもろこし」の3品を定番に、発売から半年経たずして年間の売り上げ目標を達成。翌年も新しい味を加え、快進撃は続くかのように思われた。